沖縄県石垣島の山歩き
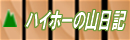
はじめに / Prologue
ヤマケイの分県・登山ガイドの石垣島の山を見ていたら頂上の尖った山があった。「石垣島の槍ヶ岳」と言ってもいいほどの山姿だ。石垣島に行ったら於茂登岳とこの山には登ろうと思っていた。
データ / Date
登山日 : 平成27年3月20日
山 名 : 野底岳(読み:のそこだけ)
標 高 : 282.4m(国土地理院の地図は281.5m)
地形図 : 伊野田
コース / Course time
登山口---(45)---分岐---(10)---頂上---(45)---登山口
端数は5分単位で切り上げ。頂上での滞在時間は含まないが、休憩時間は含む。
記 録 / Report
この山の正式名は「野底岳」だが、「ヌスクマーペー」とも呼ばれている。ヌスクは野底のこと。マーペーは女性の名前。地元では、ただ「マーペー」とも呼ばれている。その理由は後記する。バスを下り舗装路を歩くと正面に野底岳が現われる。上の写真の1枚は、登山口の手前から撮影している。地元の山岳会「山水会」さんが設置した案内板の前で準備運動の後、スタート。右側にはイノシシ除けと思われる金網が設置されている。足を踏み入れた登山道はヌカルミ状態で、歩幅に合わせてブロックが置いてある。いつも開いていると思われる金網のゲートを右に折れると、いきなり急登になる。道は迷うところのない1本道で、赤土の道には多くのロープが設置されている。45分ほどで左から合流する分岐がある。野底林道から頂上への近道だが、ヤマケイの新・分県登山ガイド46の改訂版には、現在は通行できないと記されている。
空が開けてくると、頂上直下にヌスクマーペーの由来を記した案内板がある。
その内容は、次のとおりである。
昔 琉球王国時代 役人が国王の命として 人々を一人残さず強制移住させる「道切りの法」という制度があった。
当時 黒島の宮里村のカニムイとマーペーは恋仲であったが 道切り法により 享保七年(1732)に建立された新村 野底村へマーペーは強制移住させられた。
毎日カニムイの事を思い泣きもだえていたマーペーは 近くの高い山に登ってふる里を見ようとしていたが オモト山が立ちはだかり何も見えなかった。
幾日もなげき悲しんだマーペーは 頂上で祈る姿で石となった。
その後 人々はマーペーをあわれみ この山を野底マーペーと呼ぶようになった。
八重山歴史家 牧野清 山水会
この話とは異なるが、本島には、こんな話も残っている。琉球王朝は税と労働力の確保を目的として、村人の別地域への移動を禁止していた。そんな時代に、恩納ナビーという歌人が詠んだ「恩納松下に 禁止の碑のたちゆす 恋しのぶまで 禁止やないさめ」という硫歌がある。意味は、村外に出てはならぬという立て札があろうとも 恋偲ぶ心までは、くい止めることは出来ないと言うのだが、同じく恩納ナビーの「恩納岳あがた 里の生まれ島 森を押し除きて こがたなさな」という歌もある。歌の意味は、恩納岳のあちら側には、想う人が住む村がある 山を押し除けて、こちらに引き寄せたいというのだが、恋愛も結婚も同じ村の男女同士だった時代に、隣村に想う人がいると大胆に歌ったもので、マーペーにも、こんな意思の強さがあったら、オモト岳を押し除けて恋しいカニムイの住む村を見ることができただろうに…。
頂上は大きな岩がいくつも重なっており360度の展望がある。この日は、あいにくの曇り空で海の色が沈んでいるが、晴天なら素晴らしい絶景が広がるだろう。
《お願い》Topの画像は、スライド画像です。スライド画像は、JavaScriptの使用を有効にしなければ、正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
 |
 |
 |
| 登山口 | ヌカルミの道にはブロック | 金網のゲートがある。開いていた |
 |
 |
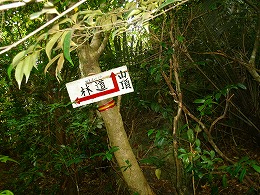 |
| 急登で始まるが、歩きやすい道もある | 赤土の急登にはロープがある | 野底林道からの近道分岐 |
 |
 |
 |
| ここから頂上まで5分 | 滑りやすい急登が続く | ヌスクマーペーの伝説 |
 |
 |
 |
| 頂上が見えてくる | 三等三角点 | 頂上からの展望。この日は曇天 |
 |
このコース地図は、国土地理院の電子国土Webにより作成したものです。
コースの赤線はアバウトです。 |
◎お願い
この日記は、登った日、当時の個人的な記録です。ヤマケイのガイドブックのように、必要な情報を網羅してはおりません。リスクは自己責任でお願いします。




